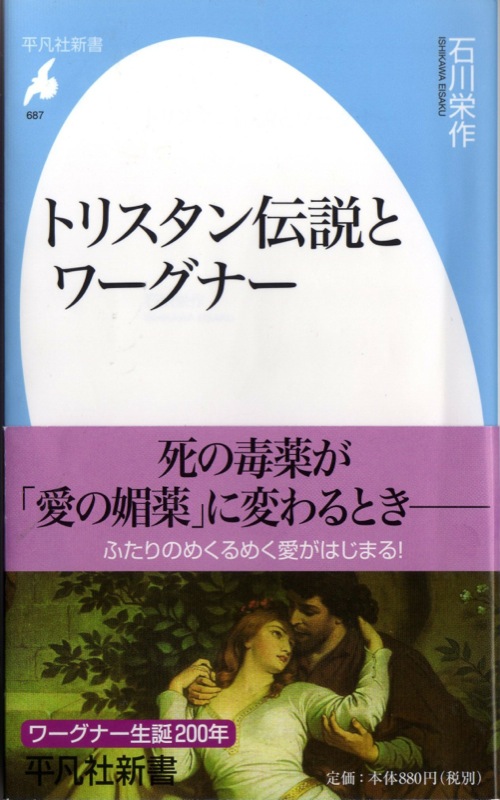
本年(2013年)6月14日、拙著『トリスタン伝説とワーグナー』が平凡社新書として刊行された。本書は、ニーベルンゲン伝説やジークフリート伝説とともに筆者が長年取り組んできたトリスタン伝説の系譜研究を一般読者向けに書き換えて、新書版で刊行されることとなったものである。本年はワーグナー生誕200年の記念すべき年でもあり、それにあわせるかたちで学部長としての激務のかたわら寸暇を惜しんで書き進めてきたが、それが実現することとなっただけに、喜びもまたひとしおである。「トリスタン伝説」と言えば、まずワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』を思い浮かべる人が多いことと思われるが、実はワーグナーの作品はトリスタン伝説の系譜においては「もはや伝説を離れて、一つの聖なる詩となっている」作品であり、特異性を有していると言っても過言ではあるまい。ワーグナーの特異性は一体どこにあるのか。本書はそのトリスタン伝説の系譜をたどりながら、ワーグナー作品の特異性を探っていったものである。ここで若干、本書の意義・特徴などを紹介することにしよう。
トリスタンとイゾルデの悲恋物語に関するいわゆる「トリスタン伝説」の起源は9世紀のケルト伝説にまで遡り、序章ではそのケルト伝説としてアイルランドに遺されている『ディアミッドとグライーネの駈落ち』と『デアドラとウスナの子たちの死』を、先人の研究を参照しながら、詳しく紹介している。いずれも女性の方が男性に「呪い」(ゲイス)をかけてその者を誘惑して駈落ちするという「駈落ち譚」であるが、これらの紹介によってトリスタン伝説の源泉であるケルト伝説が明らかになった。まずはこの点に本書の意義があるのではないかと自負している。
アイルランドで9世紀に生まれた上記の二つの「駈落ち譚」は、やがて11世紀後半になってウェールズの地と、さらにはブルターニュの地にも伝承されて、それがトリスタン伝説の原型となる。その際、アイルランドの「駈落ち譚」における「呪い」(ゲイス)は削除されて、それに代わって「フィルトル」(愛の飲料)が取り入れられる。この「愛の媚薬」の導入によって、これまでの「駈落ち譚」は新しい恋物語に書き改められ、さまざまなエピソードが付け加えられて、トリスタン伝説の原典(エストワール)が成立するのである。この原典には、第一ブロック(トリスタンの出生と養育と修業の旅)、第二ブロック(マルケ王の求婚)、第三ブロック(恋人たちの逢瀬)および第四ブロック(白い手のイゾルデ)の物語がすでに含まれていたと推定される。この原典がヨーロッパ各国の物語詩人たちの関心を呼び起こして、そこからさまざまな作品が創り出されていくのである。それらの新たな展開は大きく三つの系統に分けられる。
第一の系統は、フランスの詩人ベルールに代表されるもので、その名前をとって「ベルール系」あるいは「流布本系」とも呼ばれ、第一章でこの系統に属する作品を紹介している。フランスのベルール『トリスタン伝説』の断片に続いて、ドイツの詩人アイルハルト・フォン・オーベルクの作品『トリストラント』や、それを素材として出来上がった15世紀の民衆本『トリストラントとイザルデ』、また16世紀のハンス・ザックスの戯曲『トリストラントと美しき王妃イザルトの悲恋』(全七幕)を取り扱っている。それらの中でもアイルハルトの作品は、中世ヨーロッパでトリスタン伝説の全貌を伝える唯一の作品でありながら、これまでほとんど知られないままであったが、本書においては上記の第一ブロックから第四ブロックまでの物語をすべて詳しく紹介しており、この点についても本書は大きな意義があると確信している。この第一の系統の特徴は、物語を簡潔明瞭にテンポよく展開させているところにあると言えよう。
この第一の「ベルール系」とは対照的に主人公たちの内面的な叙述が多くなって、その内面がより深く掘り下げているのを特徴とする作品群がある。これが第二の系統であり、その系統の最初の作品を書き上げたフランスのトマに代表されるとして、「トマ系」あるいは「風雅体系」と呼ばれている。第二章においてこの第二の系統に属する作品として、トマの『トリスタン物語』の断片に続いて、そのトマの作品を素材としたドイツのゴットフリート・フォン・シュトラースブルクの『トリスタンとイゾルデ』(1210年頃)を詳しく取り扱ったあと、14世紀イギリスの中世英語詩『サア・トリストレム』を簡単に紹介している。
そのイギリスの中世英語詩『サア・トリストレム』は韻文で書かれているが、それに対してフランスでは散文で書かれたトリスタン伝説もある。「散文トリスタン」と呼ばれているものがそれであり、この第三の系統の作品はおよそ1225年から1235年の間に出来上がったが、そののち1250年以後には改作されて、膨大な量に膨れ上がったものが多くの写本や初期の印刷本として残されている。この「散文トリスタン」ではこれまでの主人公たちの物語に加えて、新しい騎士の冒険をも取り入れており、ここでトリスタン伝説は決定的にアーサー王物語に結びつけられたのである。そこにこの第三の系統の特徴がある。第三章ではその系統に属する作品として、14世紀半ばに成立したと推定されるイタリアの『ラ・タヴォラ・リトンダ』(円卓物語)と15世紀のトマス・マロリーの『アーサー王物語』におけるトリスタン伝説を紹介している。トマス・マロリーがどのようにトリスタン伝説を『アーサー王物語」の中に取り入れられているかがよく分かって、興味深い章ではないかと思っている。
こうしてトリスタン伝説は中世後期になると、アーサー王物語に結びつけられて、これまでとは異なる物語として発展を続けて、人々に親しまれていくが、しかし、16世紀になると、次第に人々の脳裏からは離れていって、しばらくは忘れ去られていた。そのような状態が長く続いたあと、トリスタン伝説が再び世に知られるようになるのは、18世紀の終わり近くになってからである。中世の作品が再び脚光を浴びる中で、やがて19世紀に入り、トリスタン伝説を一躍有名なものにしたのがリヒャルト・ワーグナー(1813-83)である。
ワーグナーは素材にトマ系のゴットフリートの作品を用いたが、しかし、出来上がった楽劇『トリスタンとイゾルデ』(1859年完成、1865年初演)は、すでに上で述べたように「もはや伝説を離れて、一つの聖なる詩となっている」と言ってもよいであろう。ゴットフリートの作品では上で述べた第一ブロックから第四ブロックの途中までの物語が取り入れられているが、ワーグナーはそれらのうちの多くを削除し、自分の作品に残しているのは、「婚礼の船旅」と「愛の媚薬」(第一幕)、「恋人たちの逢瀬」(第二幕)、そして「愛の死」(第三幕)だけであり、しかもそれらはかなり簡略化されたり、改変されたりしている。そのほかになくてはならないエピソードとして、「トリスタンとモーロルトの決闘」、タントリスと名乗っての「癒しの旅」、「剣の刃こぼれ」、「マルケ王の求婚」などが挙げられるが、それらは登場人物の台詞(せりふ)の中で回想されて語られているにすぎない。ワーグナーはドイツ中世叙事詩を素材に用いながらも、それとはまったく違うトリスタン世界を作り上げているのである。第四章においては、そのトリスタン世界についてかなりの分量を費やし詳細に述べている。本書の中心をなす部分である。
ワーグナーのトリスタン世界の特異性を要約すると、素材の簡略化はトリスタンとイゾルデの愛を内面的に深化させることにも繋がっている。しかも二人の愛は全3幕の展開に合わせるかたちで、三段階に分けて順序よく深められている。
まず第一幕で、二人の愛は「沈黙」のうちに展開され、もどかしい筋の展開となっており、それが表面に現れ出るのは、二人が盃の中に入っているものを飲んでからである。しかも二人が死を覚悟しながら、一度目の自殺行為として「死の毒薬」と思って飲んだものが、実は「愛の媚薬」だったのであり、それによってワーグナー独自のテーマが展開されることになった。
そのワーグナー独自のテーマに従って、第二幕では「昼の世界」と「夜の世界」の対立が展開され、その対立によって二人は「夜の世界」へのあこがれを強めていくが、最終場面でマルケ王やメーロトなどの「昼の世界」の登場によって、その「夜の世界」へのあこがれが遮断されてしまう。そこでトリスタンは二度目の自殺行為によって自ら強引に「夜の国」へ行こうとする。
こうして一度ならず二度まで「夜の世界」に足を踏み入れようとしたトリスタンは、第三幕においても、一人ではその「夜の世界」に入って行くことができずに、まだイゾルデのいる「昼の世界」に舞い戻って来るが、しかし、遠い昔よく耳にした「なつかしい調べ」を聞きながらイゾルデへのあこがれをいっそう強くしていって、三度目の自殺行為によってようやくイゾルデを「夜の世界」に誘い出すことができた。イゾルデは最終場面でマルケ王が姿を現しても、もはや動じない。「愛の死」を歌い上げることによって、イゾルデはあこがれの「夜の世界」でトリスタンと結ばれ、二人の愛は宇宙と一体になったのである。
このように二人の愛は第一段階では「沈黙」の殻を打ち破り、第二段階では「昼」と「夜」の対立によって「夜の国」へのあこがれを強め、第三段階においてようやく「愛」と「死」の合一を実現するのである。この「夜の国へのあこがれ」は従来のトリスタン伝説には見出されないもので、ワーグナーが初めて取り入れたものである。ここにワーグナーの特異性があると言えよう。
トリスタン伝説はこのワーグナーの作品によって新たな作品世界へと開かれ、内容はますます豊かなものとなった。その豊饒(ほうじょう)なトリスタン伝説を素材として19世紀から20世紀にかけてもたくさんの作品が作られていく。第五章ではとりわけ注目すべきフランスのベディエ編纂の『トリスタン・イズ物語』とイギリスの女流作家ローズマリー・サトクリフの『トリスタンとイズー』を取り扱ったあと、ジャン・コクトー脚本のフランス映画『永劫回帰(悲恋)』(1944年)とケビン・レイノルズ監督のアメリカ映画『トリスタンとイゾルデ』(2006年)を紹介し、最後にこのトリスタン伝説の名前を現代にまで有名にしてきたものとして日本におけるワーグナーのオペラ上演の歴史を簡単にまとめている。
以上のように、本書では9世紀アイルランドのケルト伝説から12世紀イギリスあるいはフランスのトリスタン伝説の原典(エストワール)を経て、中世時代におけるヨーロッパ各地のトリスタン伝説、19世紀のワーグナー・オペラ、20世紀の現代文学作品、さらには20・21世紀の映画作品を取り上げ、現代に至るまでさまざまなかたちで伝承されてトリスタン伝説を順にたどることによって、ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』がいかに他の作品とは異なる特異性を有しているかを明らかにしているところに、本書の大きな意義があると自負している。そのワーグナーの特異性については、本論で述べたことを結びにおいても再度要約するかたちでまとめているが、とりわけワーグナーの作品はオペラであるから、他の作品のようにすでに出来上がった作品ではなく、上演されて初めて「生成する」作品であり、演出あるいは演奏によって常に新しい作品となりうる可能性を秘めていることを新たに付け加えて、全体を締め括っている。
このようにワーグナーの作品はオペラであるから、劇場鑑賞であれ、ビデオ・DVD等による鑑賞であれ、作品を鑑賞して初めて「生成する」ものであり、常に「新しい」というところに大きな魅力がある。ワーグナーの作品に読み取られる「昼の世界」と「夜の世界」の対立は、「権力」と「愛」の対立、あるいは「社会」と「自然」の対立、「政治」と「芸術」の対立と捉えることも可能である。「権力」も「社会」も「政治」ももちろん大切であるが、それ以上に「愛」と「自然」と「芸術」も私たちの生活にとっては必要不可欠である。それぞれの対立概念が調和を保つところに理想の人間生活があると思われる。本書がきっかけとなってワーグナー作品に触れて、「芸術」と「文化」にあふれた心豊かな日常生活を送っていただければ幸いである。